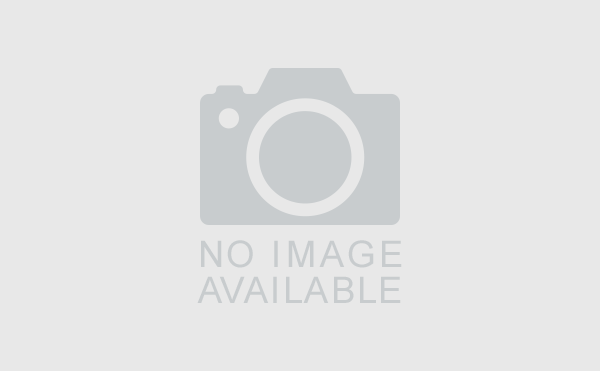【獣医師が解説】犬の子宮蓄膿症について|さいたま市大宮区のパスカル動物病院
【獣医師が解説】犬の子宮蓄膿症について|パスカル動物病院
埼玉県さいたま市大宮区、北区、見沼区、中央区、浦和区、西区の皆様こんにちは。
さいたま市大宮区のパスカル動物病院です。
メス犬に多く見られる命に関わる病気のひとつに子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)があります。
避妊手術をしていない中高齢の犬で発症することが多く、放置すると命を落とす危険が非常に高い病気です。
今回は「犬 子宮蓄膿症」について、症状・原因・治療法・予防について詳しく解説いたします。
犬の子宮蓄膿症とは?
子宮蓄膿症とは、子宮の中に細菌感染が起こり、膿がたまってしまう病気です。
発情後のホルモン変化によって子宮が細菌感染しやすい状態となり、そこに大腸菌などの細菌が繁殖して発症します。
主な症状
- 水をよく飲む(多飲)
- おしっこの量が増える(多尿)
- 陰部から膿や血の混じった分泌物が出る
- 食欲不振、元気消失
- 嘔吐、下痢
- 発熱
- お腹の張り
分泌物が出ない「閉鎖型」の場合は、外から気づきにくく症状が進行しやすいため注意が必要です。
犬の子宮蓄膿症の原因
- 発情周期によるホルモンの影響(黄体ホルモンの作用)
- 細菌感染(主に大腸菌)
- 高齢や避妊手術をしていないことがリスク要因
動物病院に行くべき目安
- 発情後数週間以内に元気がない、食欲がない
- 陰部から膿や血が出ている
- 水を異常に飲むようになった
- お腹が張ってきた
これらの症状がある場合は緊急疾患の可能性が高いため、すぐに動物病院へご来院ください。
犬の子宮蓄膿症の治療法
- 外科手術(子宮・卵巣摘出)が基本治療
開腹手術で子宮と卵巣を摘出し、根治を目指します。 - 全身状態が悪い場合は、点滴や抗生物質で全身管理を行いながら手術に備えます。
- 内科治療(薬のみ)は根本治療にならず、再発や命に関わるリスクが高いため推奨されません。
パスカル動物病院での治療
当院では、血液検査・レントゲン・超音波検査を用いて正確に診断を行います。
子宮蓄膿症と診断された場合は、全身状態を安定させた上での外科手術を基本とし、術後の管理・予防指導までサポートいたします。
ご自宅での対処法
子宮蓄膿症は自宅での対処ができない緊急疾患です。
「おかしい」と感じたらすぐに動物病院に連れて行くことが最善です。
犬の子宮蓄膿症予防
- 最も確実な予防は避妊手術
- 若いうちに手術をすることで、子宮蓄膿症だけでなく乳腺腫瘍の予防にもつながります
- 中高齢になってからでは手術リスクが高まるため、早めの検討が望ましいです
よくある質問
Q. 子宮蓄膿症は薬で治りますか?
→ 薬だけで根治はできません。手術が基本です。
Q. 手術は高齢でもできますか?
→ 状態によりますが、命を救うために高齢でも手術が必要になることが多いです。
Q. 避妊手術は何歳までにすべきですか?
→ 初回発情前〜2歳までに行うのが理想ですが、それ以降でも予防効果はあります。
まとめ
犬の子宮蓄膿症は、命に関わる非常に危険な病気です。
「発情後に元気がない」「陰部から膿が出ている」といった症状が見られたら、
迷わずパスカル動物病院にご相談ください。
予防のためには若いうちの避妊手術が最も有効です。